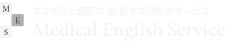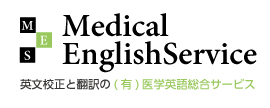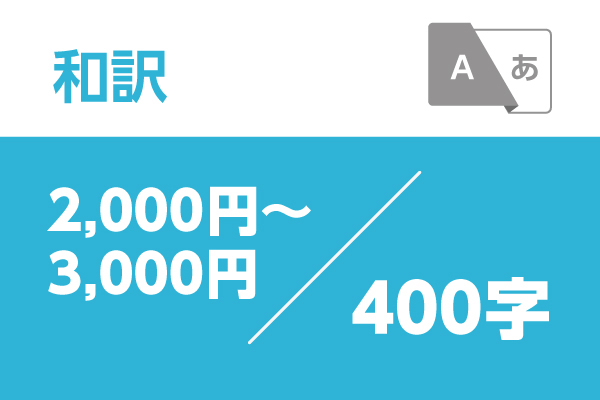各国の論文数比較から見る日本の競争力低下
近年、科学研究における日本の競争力の低下が指摘されています。その実態について、論文数を評価する複数のレポートから紐解きます。
Nature Index
Springer Nature社が2013年から毎年提供するもので、主要68誌の自然科学系学術ジャーナルに掲載された論文数を評価。68誌としたのは、自然科学系学術ジャーナルからの引用総件数の30%近くを68誌が占めると推定されるためです。Nature Indexの評価は、共著機関または共著国すべてに対して1論文を1と数えるAC、共著者の割合に応じて国や機関に論文数を割り振ったもの(FC)に、論文数が少ない宇宙物理科学に重み付けをしたWFCの2種類が公開されています。
これによると、日本のWFCは2014年までアメリカ、中国、ドイツに次ぐ第4位でしたが、2015年以降はイギリスに抜かれて第5位となっています。
Science and Engineering Indicators
全米科学財団(NSF)が2年ごとに公開している報告書。エルゼビア社のScopusに基づき、共著者の割合に応じて国や機関に論文数を割り振る方式(Nature IndexのFCと同定義)で集計します。
2014年では日本の論文数はアメリカ、中国に次ぐ第3位でしたが、最新の2016年ではインド、ドイツ、イギリスに抜かれて第6位に転落しました。なお、2016年の第1位はアメリカを抜いて中国でした。
Science and Engineering Indicators
科学研究のベンチマーキング2017
日本の科学技術・学術政策研究所(NISTEP)による報告書。クラリベイト・アナリティクス社(旧トムソン・ロイター社)のWeb of Scienceを分析対象としています。
整数カウント法(Nature IndexのACと同定義)では、日本の2003~2005年の平均は第2位だったのに対して2013~2015年の平均は第5位、分数カウント法(Nature IndexのFCと同定義)でも第2位から第4位に後退しました。伸び率を見ると、整数カウント法では横ばい、分数カウント法では減少であり、これは主要国の中で日本のみの特徴でした。
論文ベンチマーキング調査専用ページ | 科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)
日本の論文発表数の停滞が著しい
レポートによって分析対象とするデータベースは異なりますが、いずれも日本からの論文発表数が著しく停滞していることが読み取れます。その理由について、大学への運営費交付金の削減、博士号取得以降の不安定な雇用体系、研究費の過度な選択と集中、などが挙げられています。