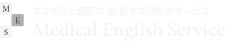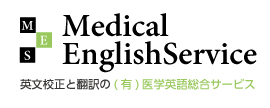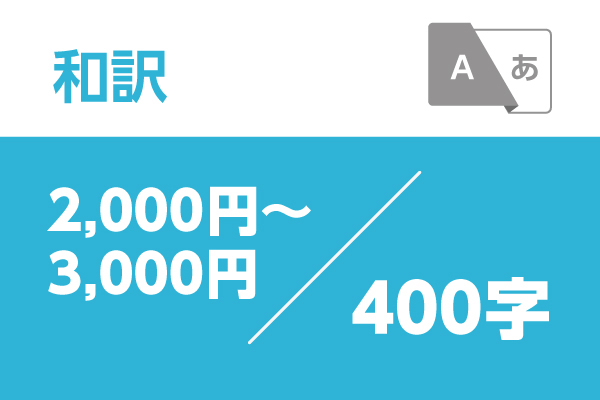粗悪な論文を大量に生産するペーパーミルに関する報告書について
近年、低品質な論文や捏造された論文を大量に生産する「ペーパーミル」が問題となっています。これらの不正な論文の増加ペースは非常に早く、わずか1.5年で倍増しており、年間に撤回された論文数を上回っていることが指摘されています。捏造データや操作された画像が用いられた不正な論文が大量に公開されることで、学術研究自体の信頼性が揺らぐ事態が懸念されます。
米国科学アカデミー紀要(PNAS)に投稿された論文“The entities enabling scientific fraud at scale are large, resilient, and growing rapidly”では、粗悪な論文を量産する業者(いわゆるペーパーミル)の存在のみならず、悪質な著者や編集者が審査担当者同士のネットワークを築き、出版の不正に加担してきたことが言及されています。
分析の方法
この論文では、Web of Science、Scopus、PubMed/MEDLINE、OpenAlexなどの学術データベースからジャーナルのデータを取得し、分析しています。さらに、学術論文の質の向上を目的として発足した、出版された論文を研究者同士が議論するWebサイトPubPeerも、10万件を超える論文に対して行われたすべてのコメントについて情報を共有しています。これらのコメントの多くは、論文の撤回に先立ち、潜在的な問題を報告しています。PubPeer上で行われた、重複した画像に関する議論についても分析しています。
・科学論文の撤回に関する事例を報告・分析するWebサイトRetraction Watchによると、2024年3月4日時点の撤回記録は47,387件
・出版済み論文のなかから問題のある論文を特定するオンラインプラットフォームProblematic Paper Screenerによると、2024年3月21日時点でペーパーミルの疑いがあるコンテンツは32,786件
その他、出版された論文の査読や審査に携わった編集者のリストや、IEEE カンファレンス、学術研究開発協会 (ARDA)など、さまざまな材料をもとに分析されました。
PLOS ONEの分析
査読つきのOAジャーナルであるPLOS ONEは、2006年の刊行以降、約20年で276,956本の論文を出版してきました。そのうち撤回された論文は702本、PubPeerでなんらかのコメントを受けた論文が2,241本となっています。
PLOS ONEは、論文の審査や編集を担当した編集者を公開しています。PLOS ONEに論文を受理した編集者18,329人について、受理した論文数および最終的に撤回された論文数を出版年ごとに調査し、偶然か有意かを分析しました。
その結果、22人の編集者については、最終的に撤回された論文を有意に高い頻度で受理していることが示唆されました。PubPeerでコメントを受けた論文を考慮すると、疑わしい編集者の数は33人に増加します。撤回された論文やPubPeerコメント付きの論文をアクセプトしたり、あるいは他のフラグ付き編集者との関係性が指摘されたりした編集者は計45名に上ります。彼らは、2024年までにPLOS ONEで発表された全論文のうち1.3%を担当していますが、撤回された論文の30.2%を担当しており、その審査や編集の精度には疑問が浮かび上がります。さらに、うち25名はPLOS ONEによって撤回された論文の著者であることも明らかとなっています。
本論文では、これらの疑わしい編集者には個人間のつながりがあることを突き止めました。4つの異なる国の機関に所属するこれらの編集者は、お互いに論文を送信し、審査を担当しあっていたことがわかったのです。この編集者グループに受理された論文の半分以上が、著者資格、利益相反、査読についての懸念などを理由に撤回されています。
こういった傾向はPLOS ONEに限った話ではなく、Hindawi誌やIEEEカンファレンスでの事例も紹介されています。
画像の重複に関する分析と分野ごとの傾向
ペーパーミルは大量の論文を一括して作成して公開すると推測されており、複数のソースから画像を断片的に流用したり組み立てたりするのではなく、固定された画像バンクを使用する可能性が指摘されています。つまり、同じタイミングで作られた複数の論文に重複した画像が用いられる可能性や、特定の出版社および特定の年に集中して後悔されることが考えられます。
実際に、本論文の分析によると、画像の重複があるとフラグ付けされた論文が2,213本、論文間の画像重複を示すエッジが4,188件観測されました。
重複した画像が用いられている論文は、本文に記述されている材料や方法にそって科学的に研究が行われているわけではないことを意味します。しかし、画像の重複が指摘されている論文のうち、撤回されたのはわずか34.1%に過ぎません。
本論文ではさらに、ペーパーミルが複数のジャーナルや出版社にまたがる出版を保証する能力を持っていること、ペーパーミルが取り扱うジャーナルのセットが需要に合わせて変化すること(ジャーナルホッピング)などが指摘されています。また、分野ごとの発生率の分析からは、ペーパーミルが好む分野やテーマも浮き彫りとなっています。例えば、RNA生物学においては、特に「miRNA」「環状RNA」「lncRNA」といったテーマでの不正が多い傾向が指摘されています。
ペーパーミルの関連が疑われる論文の多くは撤回されていない
しかしながら、これらの不正行為に対する懲罰的措置は、うまく機能していないのが現状です。例えば、不正な論文がインデックスから削除されたとしても、一部のデータベースにはその痕跡が残っています。また、論文の撤回も不正な論文の増加には追いついていません。OpenAlexによると、ペーパーミルの関連が疑われる論文29,956件のうち、撤回されたのは3割にも満たないわずか8,589件にとどまっています。
科学の完全性と信頼性を損なわないためには、研究者たちが自身の業績を水増ししようとしてペーパーミルを利用しないこと、倫理に欠けた編集者のネットワークに属さないことはもちろん、研究者がお互いの研究の信頼性を議論し、透明性のある批判と改善を積み重ねていくことが欠かせません。
参考文献
PNAS — The entities enabling scientific fraud at scale are large, resilient, and growing rapidly