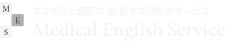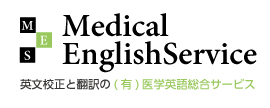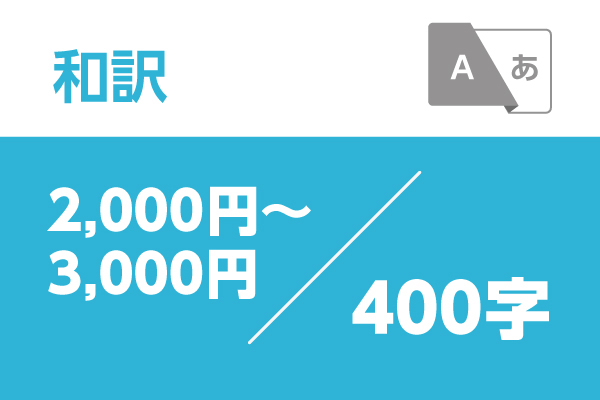『科学技術指標2025』から見る日本の研究開発費、研究人材、論文数の現状
文部科学省科学技術・学術政策研究所(NISTEP)が毎年8月に公開している「科学技術指標」は、日本および主要国の科学技術活動について分析した資料です。研究開発費、研究開発人材、研究開発のアウトプットなど計5つのカテゴリーに分けて、約160の指標に基づき分析されています。また、コラムでは近年の社会情勢を踏まえた分析が掲載されています。
本記事では、『科学技術指標2025』で報告されている日本の研究開発費や研究者数、アウトプットとしての論文数について解説します。
『科学技術指標2025』から見る日本の状況
日本の科学技術研究の動向は、前年の『科学技術指標2024』から大きく変わらず、いずれの指標も同じ順位でした。研究開発費、研究開発人材、研究開発のアウトプットの3つのカテゴリーにフォーカスしてみていきましょう。
日本の研究開発費は例年通り、米国・中国に次いで3位
主要国における研究開発費の動向を見ると、産学官を合わせた研究開発費では、米国が1位、中国が2位、そして日本(20.4兆円)が3位でした。部門別の順位を見ても、企業部門(3位)、大学部門(5位)、公的機関(4位)と、近年の順位は変動していません。
日本の企業部門における研究開発費は、米国や中国と比べて近年の伸びは緩やかであるものの、2021年から2023年にかけて1.9兆円増加しました。大学部門では、2000年代からはほぼ横ばいでしたが、同じく2021年から微増しています。
研究開発人材も例年通り、中国・米国に次いで3位
主要国における研究開発人材(研究者数)の動向は、中国が1位、米国が2位、日本(70.1万人)が3位でした。2021年に中国が米国を抜いて1位になって以降、主要7か国の順位に変動はありません。
日本の企業部門の研究者数は長く横ばいに推移しており、2017年以降に微増したものの、2024年は対前年比で1.3%減となりました。大学部門の研究者数も日本の伸びは緩やかで、現在4位のドイツが日本に迫る勢いであり、数年以内に順位が逆転するかもしれません。
研究開発のアウトプット(分数カウント法による論文数)も変わらず第5位
「研究開発のアウトプット」に関する報告では、主要国の分数カウント法に基づく論文数、Top10%補正およびTop1%補正論文が掲載されています。『科学技術指標2025』では、2021~2023年の論文数をもとに計算されています。
2021~2023年平均で見た日本の論文数は、前年(72,241本)および前々年(70,775本)より減って70,225本でした。これは中国、米国、インド、ドイツに次ぐ第5位であり、主要国の順位は前年および前々年と変化はありませんでした。
該当年の年末時点における論文の被引用数に基づいて補正を加えた補正論文数についても、主要国の順位は前年と変わっていません。2021~2023年の平均で見たTop10%補正論文数は、前年(3,719本)より減って3,447本で第13位、Top1%補正論文も前年(311本)より減って293本で第12位でした。いずれも第2位の米国においても、日本と同じく前年よりも論文数および補正論文数が減少する傾向が見られました。その一方で、第1位の中国は論文数および補正論文数ともに前年よりも増加しており、科学技術分野における中国の躍進が続いていることがうかがえます。
パテントファミリー数(特許出願数)は第1位を維持
各国・地域から生み出される発明の数について、特許出願に着目して国際比較可能な形で計測した統計をパテントファミリーといいます。このパテントファミリー数(特許出願数)では、日本は約20年前から世界第1位を維持しています。2位は米国、3位は中国となっていますが、中国は急激にパテントファミリー数を延ばし、シェアも増加しています。その一方で、日本の世界シェアは低下しており、特に「電気工学」「情報通信技術」「一般機器」分野においてはシェア縮小が顕著です。
コラム「研究用消耗品における物価高騰」について
『科学技術指標2025』のコラムでは、企業の売上高当たりの研究開発費を日米間で比較した資料や、日米中の関係に着目したハイテクノロジー産業貿易の分析などが掲載されました。そのひとつに、昨今の物価高騰を踏まえた研究消耗品の価格上昇についての分析が掲載されています。
日本の大学等における研究開発費をOECDから推計したところ、2000年代は概ね横ばいだったのに対し、研究用消耗品の単価は大きく増加しています。例えば、2010年と2024年の単価を比較すると、ヘリウムは7.2倍、診断用・研究用試薬類は4.6倍も高くなっています。これらの研究用消耗品の価格上昇はすなわち、実質的に使用できる研究開発費が少なくなっていることを示しています。昨今の物価高騰は、研究活動の持続可能性に大きな影響を与えているといえます。
関連記事:『科学技術指標2024』に見る日本の論文数推移