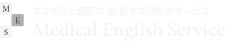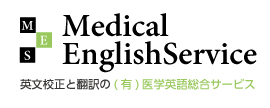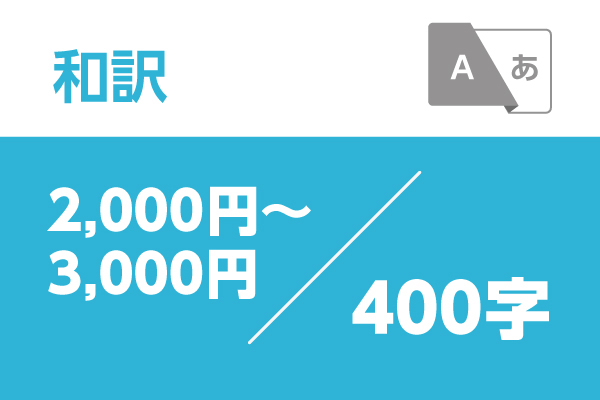シュプリンガーネイチャー社および科学技術振興機構(JST)による研究公正の取り組み
シュプリンガーネイチャー社が2024年に出版した一次研究論文は、48.2万件以上に上ります。学術研究界に大きな影響を与える同社にとって、これらの論文の信頼性を維持することは重要な責務といえます。そのため、同社はさまざまな活動やAIツールへの投資などを通して、学術記録の公正性および正確性の維持に取り組んでいます。
ここでは、シュプリンガーネイチャー社が行っている研究公正のための主な取り組みについて解説します。また、科学技術振興機構(JST)が公正な研究活動を推進するための取り組みとして制作している研究倫理映像教材についても紹介します。
研究論文の信頼性を確保するためのチェック工程
シュプリンガーネイチャー社の出版プロセスでは、複数の段階において研究論文の信頼性を維持するためのチェックが組み込まれています。編集者や専門家チームによるチェックはもちろん、AIツールも活用されています。
2024年に同社から出版された一次研究論文は48.2万件以上ですが、実際には230万件を超える論文が投稿されており、非常に多くの論文が信頼性チェックを通過できずリジェクトされていることがわかります。
具体的には、以下の5つの工程があります。
1.AIツールによる自動チェック
重複投稿、撤回された論文の引用、AI生成によるナンセンスなテキストなどをチェックします。最終的な判断は、編集者が行います。
2.編集部による一次品質チェック
図、引用、参考文献、表のチェックのほか、倫理声明、利益相反、著者の貢献、臨床試験、資金提供者に関する情報などの記載漏れがないかを初期校正段階でチェックします。
3.編集者による一次審査
シュプリンガーネイチャー社は、世界中にいる17万4,000人以上もの外部編集者と協力しています。高度な専門知識をもつ外部編集者により、研究の対象範囲は適切か、研究の新規性はあるか、盗用・剽窃がないか、画像は改ざんされていなかなどが審査されます。
4.査読および編集者による決定
さらに、シュプリンガーネイチャー社は120万人以上の査読者と協力しており、学術研究の質および公正性を評価する査読が行われています。その後、編集者の最終的な判断に基づき、出版の可否が決定します。必要に応じて、研究公正チームによる追加チェックが行われることもあります。
5.出版後の精査
出版された論文は多くの専門家に読まれ、広く精査されることになります。万が一、論文に対する懸念が指摘された場合は、同社の研究公正専門チームによって調査が行われます。必要に応じて、修正、補遺、問題提起、編集者による注記または懸念表明、そして論文の撤回などの編集措置が講じられます。なお、出版後精査の結果、2024年には2,923件の論文が撤回されました。
シュプリンガーネイチャー社が行っている研究公正のための取り組みには、この他にも、さまざまな研究コミュニティとの協力や支援、AIツールをはじめとする最新テクノロジーの活用、研究公正に特化したワークショップやオンライン教材の無料公開などが挙げられます。
研究公正を支援するAIツール
シュプリンガーネイチャー社は近年、研究公正の取り組みを支援するためのさまざまなAIツールを次々に開発・公開しています。
Geppetto(現在はSTM Integrity Hubに統合)
ペーパーミルの典型的な特徴でもある、AIが生成したナンセンスなテキストを検出するAIツールです。編集者や査読者の時間を無駄にしないために、AI生成による偽の論文を特定します。
SnappShot
論文中に使用されている画像の公正性を分析するAIツールです。画像の不正処理、重複したデータ、改ざんされたデータを検出するほか、誤って図が重複しているケースなどもチェックできるので、図表に関する著者へのフィードバックも支援します。
無関係文献チェッカーツール(The irrelevant reference checker tool)
各参考文献とその論文との関連性を分析し、無関係な参考文献を特定するAIツールです。複数の参考文献の関連性が低いと判断され、フラグ付けされた論文を、シュプリンガーネイチャー社の研究倫理グループが手作業で確認します。
非標準語句検出ツール(The non-standard phrases detector tool)
剽窃チェックを回避するためにパラフレーズツールなどを使用したと思われる、不自然な構成や複雑すぎる語句を検出するツールです。Problematic Paper Screenerとして公開されている難解フレーズの一覧を使用して開発されています。
科学技術振興機構(JST)が制作する研究倫理映像教材
科学技術振興機構(JST)も、公正な研究活動を推進するためにさまざまな取り組みを行っています。その一環として、研究倫理教育を支援するための映像教材「倫理の空白」シリーズが制作されています。大学での講義や研究機関での講習、eラーニングでの活用が想定されています。
ドラマ形式の映像教材であり、シリーズ1作目の「理工学教室編」では、学生・若手研究者と准教授それぞれの視点から、研究倫理について描かれました。2作目以降は、自然科学分野と人文・社会科学分野に分かれています。2作目では「盗用」、3作目では「研究活動のグレーゾーン」として、サラミ論文やオーサーシップ、二重投稿、自己盗用といった不正行為を描いています。
2025年5月に公開されたシリーズ4作目は、3作目に引き続き「研究活動のグレーゾーン2」がテーマとなっています。自然科学分野編では実験データの不正な選別について、人文・社会科学分野編では再現実験における仮説の後付けについて描かれています。いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれるこれらの研究行為は、不正行為として認定される可能性がある疑わしい研究行為(QRP)であり、映像教材を通して視聴者がシチュエーションを疑似体験することで、公正な研究に欠かせない判断力や責任感を養います。
研究倫理映像教材「倫理の空白Ⅳ 研究活動のグレーゾーン2」
URL:https://www.jst.go.jp/kousei_p/measuretutorial/mt_movie.html
出版プロセスでのチェックやツールの活用だけでなく研究者の倫理教育も重要
シュプリンガーネイチャー社の取り組みのように、出版プロセスにおいて何段階もチェックしたり、最新のツールを活用したりするだけでなく、JSTの映像教材のような倫理教育も重要です。仕組みやツールで研究不正を防ぎつつ、研究者自身が不正行為について理解し、責任をもって研究活動を行うことで、学術研究分野の公正性や信頼性が維持されるのです。
参考文献
Springer Nature — 研究公正
Springer Nature — 【お知らせ】シュプリンガーネイチャーにおける研究公正の取り組みを紹介するページを公開
Springer Nature — PRESS RELEASES — Springer Nature expands its portfolio of research integrity tools to detect non-standard phrases
Springer Nature –【プレスリリース】シュプリンガーネイチャー、非標準的な表現の検出ツールを導入し、研究の公正性を確保するためのツールのポートフォリオを拡大
nature asia — シュプリンガーネイチャー、研究の信頼性を守るための2つの新たなAIツールを発表
科学技術振興機構 — 研究倫理映像教材「倫理の空白Ⅳ 研究活動のグレーゾーン2」のオンライン公開について