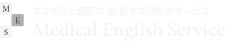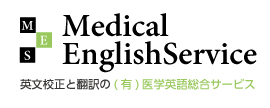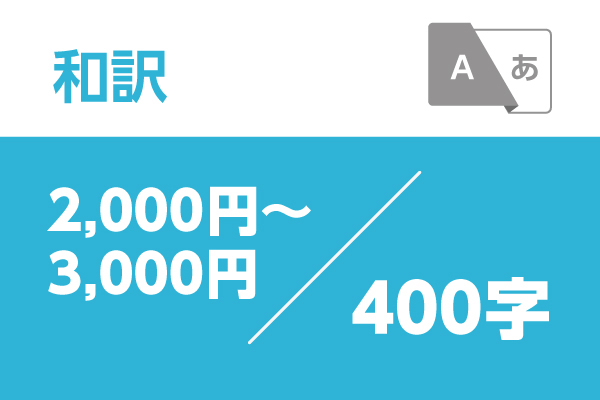Nature誌ですべての論文に適用される「透明性の高い査読(TPR)」とは
論文および査読の透明性は、学術研究において重要な要素であり、科学的なプロセスの信頼性の向上においても不可欠といえます。そのためSpringer Nature社は、出版の公正性や透明性、信頼性の向上に向けて長年取り組んできました。NatureおよびNature Communicationsが取り組んできたオープンな査読に関する経緯と、2025年6月16日からすべての掲載予定の論文に適用される「透明性の高い査読(TPR)」について解説します。
著者が希望した場合に査読報告書を公開する試験的な取り組みの経緯
Nature誌の査読にはシングルブラインド方式が採用されており、誰が自分の論文を査読しているのかを著者が知ることはできず、査読報告書の内容や著者・査読者・編集者間で交わされるやり取りも機密扱いとなっていました。しかし、論文の著者と査読者の間で交わされた議論は、その研究への理解を深める際に有用な情報です。そこで、Nature誌では2020年2月以降、著者の希望があった場合に限り、査読レポートや著者からの回答を掲載論文とあわせて公開してきました。この試験的な取り組みによって、読者は著者と査読者の間でどのような議論が交わされたのかを知ることができるようになりました。
なお、Nature Communications誌は2016年より、先駆けてこの取り組みを進めてきました。約10か月間の試験運用期間に論文が掲載された著者のうち、約60%がこの「透明性の高い査読」を選択したといいます。そして、2022年からはNature Communicationsに掲載されるすべての論文に対し、透明性の高い査読が適用されています。
Nature誌における透明性の高い査読(TPR)の自動適用の開始
Nature Communicationsの事例に続き、2025年6月16日以降、Nature誌に掲載予定のすべての一次研究論文に対して、透明性の高い査読(TPR:Transparent peer review)が適用されることになりました。論文が掲載される際、査読報告書とそれに対する著者の返答が一緒に公開されます。これは、科学的な議論の可視性を高め、オープンサイエンスの原則を推進するものとして期待されています。
なお、査読者は、匿名のままもしくは氏名を公開するかを選択できます。査読者が公開を希望しない場合は、従来通り匿名のままで掲載されます。2020年から行われていた試験的な取り組みにおいては、匿名性があっても査読者が批判的になったり、査読者の負担が増大したりすることが懸念されていましたが、先駆けて取り組んできたNature Communicationsの経験に基づき、この懸念は払拭されたといいます。
査読報告書の公開は研究の透明性や査読者の業績にとって有益
希望に応じて査読者の匿名性を維持しつつ、査読の経緯をオープンにすることで、査読者と著者の間で行われた議論にすべての読者がアクセスできるようになります。ブラックボックスとみなされやすい査読過程の透明性と信頼性の向上につながることでしょう。
また、査読報告書を読み込むことで、論文が掲載されるまでの科学的なコミュニケーションを知ることができ、若い研究者やその分野でのキャリアが浅い研究者にとっても非常に有益といえます。さらに、査読報告書の公開によって、査読自体が研究者にとっての「業績」になることも考えられます。透明性の高い査読(TPR)の取り組みがNature誌のすべての論文に適用されることで、今後、学術研究分野にとってどのような効果や変化をもたらすのか注視しましょう。
参考文献
Curren Awareness Portal — Nature誌、新規投稿論文について、論文公開時に査読コメントと著者からの回答も併せて公開へ
Springer Nature — 【プレスリリース】Nature掲載のすべての新規投稿論文に対し、透明性の高い査読を標準化
nature — Transparent peer review to be extended to all of Nature’s research papers
nature — Nature will publish peer review reports as a trial
nature asia — Nature Communicationsでは、透明性の高いピアレビューを本格導入